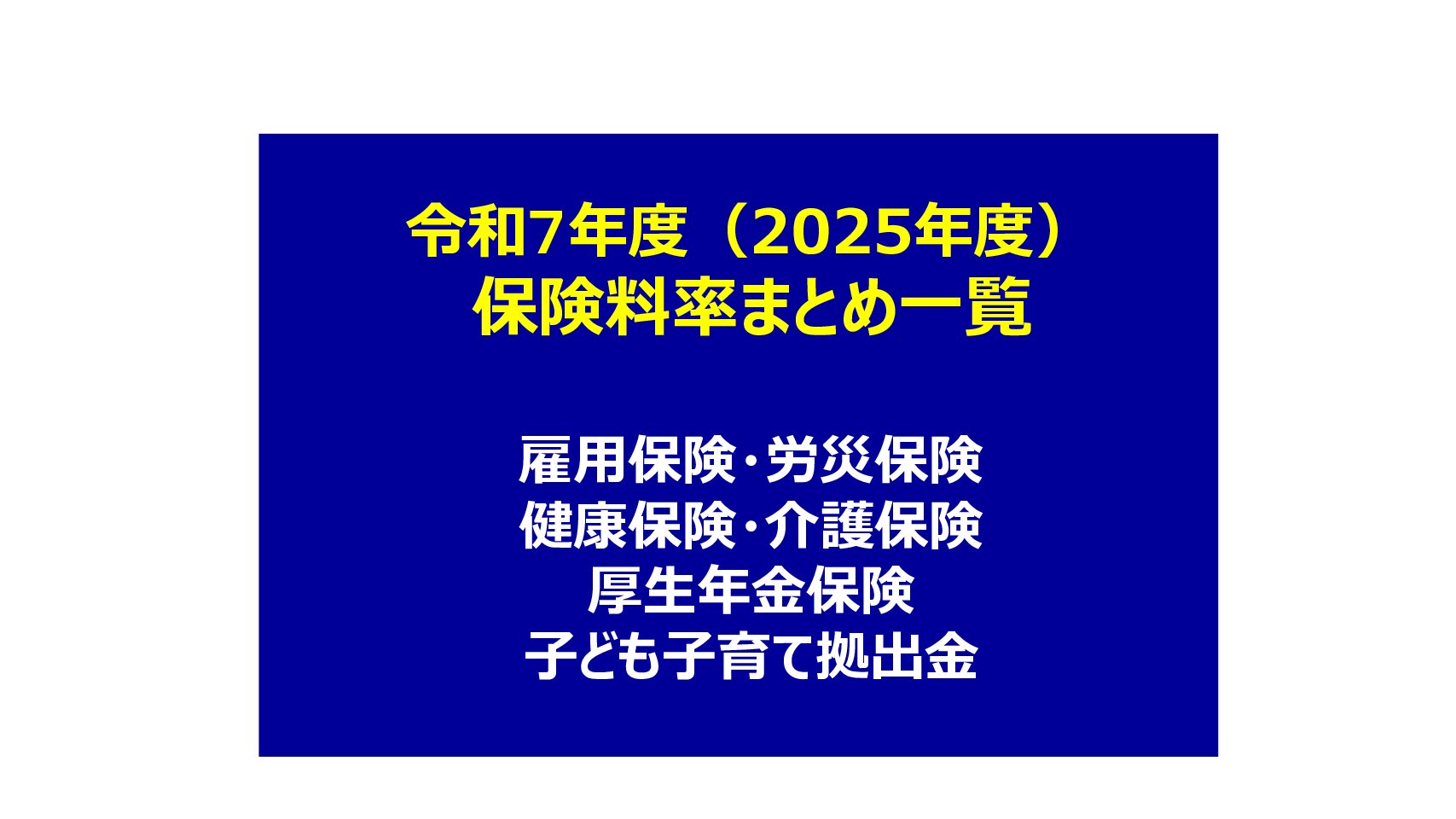会社から支給される通勤手当は、所得税が課税されない非課税限度額が設けられておりますが、自動車等利用者の通勤手当の非課税限度額が令和7年4月1日に遡って改正される可能性が出てきました。
国家公務員の給与改善に関する人事院勧告がその発端です。今回の改正は、多くの自動車通勤者にとって朗報となる一方で、企業の人事・経理担当者にとっては、年末調整での対応に注意が必要となります。
本記事では、この非課税限度額改正の背景と具体的な内容、そして企業が今後取るべき対応策について解説します。
1. なぜ今、非課税限度額が見直されるのか?
通勤手当の非課税限度額は、従業員の通勤にかかる実費を考慮して定められています。しかし、昨今のガソリン代高騰や物価上昇、そして公共交通機関の利便性が低い地域での自動車通勤者の増加といった社会情勢の変化に伴い、従来の非課税限度額では、実態にそぐわないケースが増えていました。
そのような背景の中、令和7年8月7日に発表された令和7年人事院勧告が大きな動きとなりました。人事院勧告とは、国家公務員の給与水準を民間企業の状況に合わせて見直すための勧告です。この勧告の中で、自動車などの交通用具使用者に対する通勤手当の額を増額するよう提言されました。
この人事院勧告の内容が、所得税法上の非課税限度額の改正に反映されるのが通例です。そのため、今回の勧告は、民間企業で働く私たちにも直接的な影響を与えることになります。
2. 人事院勧告の3つのポイントと遡及実施の「罠」
今回の勧告内容は、自動車等で通勤する従業員の通勤手当に関して、以下の3つのポイントで改善が図られます。
ポイント① 新たな距離区分の新設(令和8年4月実施)
現行の通勤手当は、60km以上で上限が定められていましたが、改正後は65km以上から100km以上までの5km刻みの距離区分が新設されます。これにより、長距離通勤者の負担が軽減され、非課税限度額の上限も最大66,400円まで引き上げられることになります。これは、遠方から通勤する従業員にとって、手取り収入が増える大きなメリットとなります。
ポイント② 現行区分の引上げ(令和7年4月遡及実施)
今回の改正で最も注意すべき点が、この「現行区分の引上げ」です。現行の「60km以上」までの距離区分についても、民間の支給状況を考慮し、200円から7,100円までの幅で引き上げが勧告されました。
この引き上げ分は、令和8年4月からの実施ではなく、令和7年4月1日からの遡及適用となる点が重要です。
つまり、令和7年12月に行う年末調整では、すでに始まっている令和7年4月からの通勤手当に対して、非課税限度額が新しい基準で適用されることになります。企業側は、この遡及適用分を適切に計算し、源泉徴収額を調整する必要が出てきます。
ポイント③ 駐車場の利用に対する手当の新設(令和8年4月実施)
これまでは、通勤手当に駐車場の利用料は含まれていませんでしたが、改正後は1ヶ月あたり5,000円を上限として、駐車場などの利用に対する通勤手当が新設されます。これは、都心部など駐車場代が高額な地域で働く従業員にとっては、手取り収入が増える大きなメリットとなります。この項目は、令和8年4月からの実施が予定されています。
3. なぜ年末調整で注意が必要なのか?
今回の改正、特にポイント②の「現行区分の引上げ」が令和7年4月1日に遡及して適用されることから、年末調整で特別な対応が求められます。
通常、毎月の給与から源泉徴収される所得税は、その月の給与や手当に基づいて計算されます。しかし、令和7年4月以降に支給された通勤手当は、改正前の非課税限度額に基づいて処理されているため、非課税額が過小に計算されている可能性があります。
年末調整は、その年の所得税の過不足を精算する手続きです。今回の改正によって、従業員の通勤手当の非課税限度額が増加し、結果として課税所得が減少するため、従業員から源泉徴収した所得税額が本来よりも多くなっている状態が生じます。
年末調整では、この過剰に徴収した所得税を従業員に還付する作業が必要となります。国税庁もこの点について、年末調整での対応が必要となる可能性があることを予告しており、企業の人事・経理担当者は、改正内容を正確に把握し、適切な処理を行うための準備が不可欠です。
4. 企業が今から準備すべきこと
今回の改正は、今後の企業の給与計算や年末調整に大きな影響を与えます。混乱を避けるためにも、以下の点を今から準備しておくことが重要です。
① 最新情報の継続的な確認
人事院勧告はあくまで提言であり、最終的な法改正は国会での審議を経て決定されます。国税庁の公式発表や、関連法令の改正情報を継続的に確認しましょう。特に年末調整時期には、国税庁の特設ページなどが公開される可能性が高いため、こまめなチェックが不可欠です。
② 従業員への周知とヒアリング
今回の改正は、特に長距離通勤者や駐車場を利用している従業員に大きな影響を与えます。改正内容を事前に周知し、通勤距離や駐車場利用の有無などを正確に把握するためのヒアリングを行うことで、スムーズな年末調整の準備を進めることができます。
③ 給与計算システムの確認と更新
多くの企業では、給与計算ソフトを利用しています。しかし、今回の改正のような遡及適用の場合、通常のバージョンアップだけでは対応できない可能性があります。ソフトウェアベンダーに確認し、遡及分を正確に計算できる機能が提供されるか、またどのような手順で処理すべきかを事前に把握しておきましょう。
④ 年末調整業務のシミュレーション
年末調整の時期が迫ってから慌てないよう、今回の改正を考慮に入れたシミュレーションを行っておくことも有効です。対象となる従業員を特定し、還付されるおおよその金額を算出することで、本番での混乱を最小限に抑えられます。
⑤ 4月以降の退職者の源泉徴収票の再作成が必要かどうかのチェック
今回の非課税限度額の改正は令和7年4月に遡及して適用されるため、4月以降に退職した従業員の源泉徴収票に影響する可能性があります。既に交付済みの源泉徴収票に誤りが生じる場合は、再作成・再交付が必要となるため、対象者を特定して確認しておきましょう。
⑥ 就業規則(賃金規程)への影響のチェックと変更
就業規則や賃金規程に「通勤手当は非課税限度額内で支給する」といった規定を設けている場合、今回の改正により規定内容と実務が乖離する恐れがあります。労使トラブルを避けるためにも、規程上の記載が改正後の実務に適合しているかを確認し、必要に応じて変更手続きを進めることが重要です。
まとめ:変化を味方につけ、円滑な年末調整を
自動車通勤手当の非課税限度額の改正は、多くの従業員にとって歓迎すべきニュースです。しかし、その裏側で、企業の人事・経理担当者には正確かつ迅速な対応が求められます。
令和7年の年末調整は、この遡及改正によって例年以上に注意が必要です。国税庁からの最新情報にアンテナを張り、従業員とのコミュニケーションを密にし、給与計算システムを適切に更新することで、この変化を乗り越える必要がありそうです。
〈参考〉
◆人事院「令和7年 人事院勧告」
https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html
◆国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/index.htm
◆国税庁「No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
-コピー-1.png)